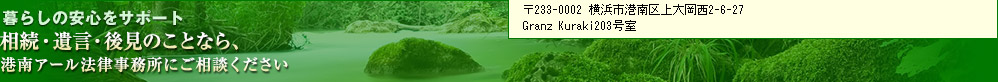
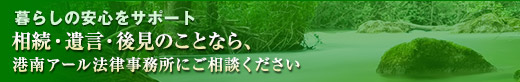

高齢者の暮らしのご相談なら、横浜市上大岡の法律事務所、港南アール法律事務所にご相談ください

※無断転載、引用はお断りしています。
お兄さんについて、遺産分割協議を行えるだけの判断能力が無い場合には、成年後見制度を利用することが考えられます。
例えば、お兄さんが医師から「成年後見相当」と診断を受けた場合には、後見開始の審判を申立て、後見人が選任されたら、成年後見人と遺産分割協議を行うことが考えられます。
任意後見契約を締結していても、任意後見人は代理権目録に記載されていない事項については、代理権を有しません。そのため、代理権目録に記載されていない事項を、お母さんに代わって行うことは出来ません。
この場合、改めて任意後見契約を結んで代理権目録への記載事項を増やすことが考えられますが、契約を行うだけの判断能力がない場合には、成年後見制度を利用することが考えられます(任意後見契約に関する法律第10条1項参照)。
申立てを行う際、家庭裁判所に提出する書類として「本人の診断書」が要求されています。ただ、この診断書の提出は法律上必須とされているわけではありません。
そのため、本人の診断書がどうしても取れない理由がある場合には、事情を説明した上で、診断書を提出しないまま申立てをすること自体は可能と考えられています。
ただ、本人の判断能力の程度を把握した上で、本人の判断能力が成年後見、保佐、補助のいずれに該当するかを予め把握しておくことも大切ですし、、この診断書の作成は精神科医に限定されていない、とされていますから、なるべく本人に説明・説得をするとともに訪問診療を行ってくれる医師に協力を求めるなどして、診断書は準備をした方が良いと思われます。
この場合には、法定相続人は前夫との間の子と、今の夫が法定相続人になります。
再婚相手の連れ子は、あなたと養子縁組をしていない以上、親子関係が生じないため、あなたの法定相続人にはなりません。
法定相続人は順に①子、②直系尊属、③兄弟姉妹とされています(民法887条、889条参照)。
また、配偶者は常に法定相続人となります(民法890条)。
そのため、この場合の法定相続人は今の妻と、今の妻との間の子ども2人、前妻との間の子ども1人の4人です。
成年後見人を就任させるためには、まずは後見開始審判の申し立てを行う必要があります。
この時、申立をする人の代理人として家庭裁判所で手続が出来るのは、弁護士に限られています。そのため、申立人に代わって裁判所と直接やり取りを行うことが出来るのが大きなメリットと考えます。
また、弁護士は紛争になってしまった事案を多く取り扱っていますので、そこから問題が起きないようにするためには、どのような対応をすべきかというアドバイスも行うこともできます。
このように、後見に限らず、様々な観点から依頼者のサポートが行えることも大きなメリットであると考えます。
後見人の報酬については、家庭裁判所が被後見人の資力などを考慮し、その財産の中から相当な報酬を与えることができるとされています(民法862条参照)。
そのため、後見人が勝手に被後見人の財産から引き出すことは出来ず、家庭裁判所に報酬付与の審判を申立て、報酬額を決めてもらう必要があります(保佐人、補助人も同様です)。
後見開始などの申立ての際に、本人の親族の同意は要件にはなっていません。そのため、親族が反対している場合であっても、後見開始などの申し立てを行うことは可能です。
家庭裁判所に申し立てを行う際には、親族の同意書の提出が求められますが、これはあくまでも裁判所が審理の際に参考にするため、また同意があった方が手続が比較的スムーズに進むためとされています。
そのため、親族の同意を取れないような場合であっても、後見制度を利用することは可能です。
民法では被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に「遺留分」を設けています(民法1028条以下)。
そのため、遺留分が侵害されている場合、お兄さんに対して、遺留分減殺請求権を行使することができます。
その上で、お兄さんと話し合いがつけば問題はありませんが、話し合いがつかない場合には、調停を申し立てたり、訴訟を提起するなどして裁判所において解決を図ることが考えられます。
後見人は被後見人の身上監護、財産管理のための事務を行う必要があるので、成年被後見人に近いところに住んでいる親族や、その地域で開業している弁護士を候補者にすることが考えられます。
もっとも、親族がいなかったり、知り合いの弁護士がいないといったように、適当な候補者が見つからない場合も考えられます。
その場合には、裁判所と協議をした上で、候補者を裁判所に一任することも考えられます。