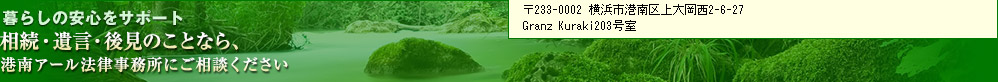
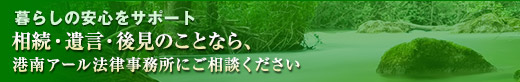

高齢者の暮らしのご相談なら、横浜市上大岡の法律事務所、港南アール法律事務所にご相談ください

※無断転載、引用はお断りしています。
事実婚である内縁関係には、現状では相続権は認められていません。 したがって、内縁の妻は、内縁の夫の遺産に関して相続権はありません。
夫の姉が建物の明渡を求めた場合、①内縁の夫の死後は、無償使用することを許すという黙示の合意があった(参照:名古屋地方裁判所平成23年2月25日/判例時報2118号66頁など)や、②夫の姉の主張は権利の濫用として許されない(参照:東京地方裁判所平成9年10月3日/判例タイムズ980号176頁)と反論して、自宅に居住し続けることを主張することも考えられますが、争いになることは避けられません。
これを防ぐためには、内縁の夫に「自宅を内縁の妻に遺贈する」といった内容の遺言を作成しておいてもらうことが考えられます。
まず、そもそもお父さんの遺言が無効だと主張する場合が考えられます。例えば、遺言作成時には認知症などで、遺言作成能力が全く認められなかった場合や、そもそも別人が書いたと思われる場合などに、そのような主張をすることが考えられます。
もっとも、そのような事情が無い場合には、遺言が有効であることを前提として、遺留分減殺請求を行うことが考えられます。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分と言って、相続財産に対して一定の割合で権利が保障されています。そのため、上記請求を行い、一定割合で相続財産を確保することが考えられます。
なお、同請求は、請求権のある権利者が相続の開始・遺贈・贈与があったことを知った時から1年、相続開始から10年経過するとできなくなるので、注意が必要です。
どの形式の遺言書を作成する場合でも、事前にご自身が所有している土地・建物や、預貯金、株式などの有価証券といった財産がどれだけあるのか確認しておく必要があります。
このとき、借入れなどのマイナスの財産も忘れずに確認してください。
次に、その財産を相続する権利のある人(法定相続人)が誰になるのかを明らかにしておく必要があります。法定相続人は、民法によって定められていますので、まずはご自身が生まれてから現在までの戸籍を取り寄せるなどして、ご自身の法定相続人が誰になるのかを確認しましょう。
その上で、ご自身の財産をどのように相続させるのかを検討する必要があります。なお、法定相続人ではない人に対しても、遺贈という形で財産を渡すことも可能です。
証人には未成年者、推定相続人、受遺者、これらの配偶者・直系血族、公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記、使用人はなれないとされています(民法974条参照)。
そのため、まずはこれら以外の人から選ぶ必要があります。
そして、遺言の内容を把握できることから、信用できる人を選ぶ必要があります。
当事務所では、遺言作成に関与している場合、ご希望に応じて弁護士が証人として遺言作成の場面に立ち会っております。
長男の妻に自分の財産を全て遺贈する、という趣旨の遺言を残しておくことで、長男の妻に自分の遺産を残すことは可能です。
もっとも、次男があなたの意図を汲み取れなかった場合、長男の妻に対して、「遺留分減殺請求権」を行使するなどして、トラブルが生じることも考えられます。
そのため、まずは弁護士に相談をした上で、遺言の内容を決めることをお勧めします。
民法では被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に「遺留分」を設けています(民法1028条以下)。
そのため、遺留分が侵害されている場合、お兄さんに対して、遺留分減殺請求権を行使することができます。
その上で、お兄さんと話し合いがつけば問題はありませんが、話し合いがつかない場合には、調停を申し立てたり、訴訟を提起するなどして裁判所において解決を図ることが考えられます。
相続人が遺言(公正証書遺言を除く。)を発見した場合、速やかに家庭裁判所に提出し、検認を請求しなくてはいけないとされています(民法1004条1項)。
また、封印がある遺言書は、裁判所以外では開封できないとされ、裁判所外で開封をしてしまった場合には、5万円以下の過料に処するとされています(民法1004条3項、同1005条)。
そのため、この場合には開けることなく、速やかに家庭裁判所に対して、検認の請求を行うべきです。
公正証書遺言を作成する際には、証人が2名以上立ち会う必要があり(民法969条1号参照)、未成年者や推定相続人・受遺者とこれらの配偶者・直系血族、そして公証人の配偶者や四親等以内の親族、書記及び使用人は証人になれません(民法974条参照)。
ですので、公正証書遺言を作成する場合にご家族が証人になれない、というケースはよくあります。
他方で、証人は公正証書遺言の内容を全て確認することから、信頼できる人を選ぶ必要があります。
そのため、当事務所では公正証書遺言を作成する場合に、適当な証人がいない方には、弁護士らが証人として公正証書遺言作成に立ち会う、といったことも行っております。
自筆証書遺言の場合、亡くなられた方がどこに保管していたか分からないと、探すのは困難です。金庫や金融機関の貸金庫に入れている方もいるようなので、思い当るところを探すほかないと思われます。
他方で、公正証書遺言や秘密証書遺言であれば、昭和64年以降に作成している場合には、相続人であればどこの公証役場からでも検索をすることが可能です(それより前に作成した場合には、作成した公証役場であれば検索は可能とのことです)。
その際に必要な書類や詳細は、近くの公証役場にお問い合わせください。
あなたが亡くなった場合には、お子さんが相続人のとなることから、原則としてお子さんが財産を全て相続することになります。
そのため、あなたがお子さん以外に財産を渡したいのであれば、まずは自分の財産を渡したい人に財産を遺贈する旨の遺言を作成しておくことが考えられます
自筆証書遺言はその全文、日付、氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされているので(民法968条1項)、その要件を満たさない以上、自筆証書遺言としては無効になってしまいます。
長い文章をご自身で書けない場合でも、公正証書遺言を作成することは可能ですので、そちらをお勧めします(なお、秘密証書遺言は全文を自筆で書く必要まではありませんが、その他民法が定める要件を満たす必要がありますので(民法970条)、ただ単にパソコンで印刷したものに署名・押印をするだけでは要件を満たしません)。
遺言は民法の定める方式に基づいて行わなければならないとされているので(民法960条参照)、録画や録音によるメッセージがあったとしても、それは法律上の遺言としては無効です。
字が書けない場合であっても、公正証書遺言を作成することは可能ですので、公正証書遺言の作成をお勧めします。
遺言は15歳以上で、遺言作成時に遺言能力を有していれば作成することができます(民法961条、963条)。
そのため、認知症の疑いがあれば、絶対に遺言作成が出来ないというわけではないと考えられますが、意思能力がすでに失われているような状態では、遺言を作成することはできないと考えられます(そのような状態で作成された遺言については、後で無効と主張され、争いが生じる可能性もあります)。
ですので、まずは医師の診断を仰ぎ、遺言を作成できるだけの意思能力が残されているかどうか、を確認する必要があります。
遺言者は遺言を作成した後でも、遺言の方式に従って撤回をすることが出来ます(民法1022条)。
また、新たに作成した遺言が前の遺言と抵触する時には、抵触した部分については後の遺言で撤回したものとみなされます(民法1023条)。
そのため、気が変わった場合には、新たな遺言を作成して、前の遺言の内容を撤回することが可能です。
公証役場まで行くことが出来ない理由がある場合、公証人にお母さんがいるところまで出張してもらって、公正証書遺言を作成することは可能です。
ただし、この場合には通常よりも手数料がかかることになり、また出張日当や交通費がかかることになります(具体的な費用については、お近くの公証役場にお問い合わせください)
なお、当事務所では高齢で外出が困難な方に対しては、ご自宅などへのの出張法律相談も実施しております。
お気軽にお問い合わせください。
葬儀費用(通夜・告別式、火葬の費用など)は相続開始後に生じた債務であり、また一時的には喪主が負担することから、相続人全員の合意がなければ、当然に遺産から清算をすることは出来ません。その場合には民事訴訟などでその負担について解決することになります。
もっとも、相続人全員の合意が得られれば、葬儀費用を遺産から清算した上で、残りの遺産を分割するといったことも可能です。
民法上、同一の遺言証書で2名以上の者が遺言をすることはできないとされているので(民法975条)、原則として無効となってしまいます。
それにより、争いが生じてしまうことにもなりかねませんので、遺言はお一人ずつ作成してください。
遺言はその人が満15歳以上であれば、作成することができます(民法962条)。
そのため、ご本人が必要性を感じた時点が、遺言作成のタイミングだと思われます。
もっとも、注意しなくては行けないのは、遺言を作成する時点では、遺言能力が必要です(民法763条)。
そのため、例えば認知症になってしまった後に遺言を作成した場合、ご本人が無くなった後で、ご本人に遺言作成の時点で遺言能力があったかどうか、つまりその遺言の有効性が争われる可能性が出て来てしまいます。
ですので遺言は必要性を感じたら、健康なうちに、なるべく早く作成しておくことをお勧めします。
弁護士に頼むと費用が高い、と気にされる方はとても多いと思います。
当事務所では、初回相談の際、具体的に依頼を頂いた場合に「弁護士がどのようなことができるのか。」、「どれくらい費用が必要なのか」について説明させていただいております。
また、その場では依頼をするかどうか決められない場合がほとんどだと思いますので、ご希望に応じて見積書を無料で発行しております。
それと、当事務所にご相談いただいた方の中にも、「相談をするのにもとても費用がかかるのではないか、と心配されて今まで相談にいけなかった」、という方もいらっしゃいました。
なるべくお気軽にご相談いただけるように、相続、遺言、成年後見といった一定の事案については、初回の法律相談料を無料とさせていただいております(1時間無料ですが、事前にご準備いただければ、1時間以内に回答を行える場合がほとんどです)。
費用に関しては聞きづらいところだと思いますが、大切なことですので、相談の際にもご遠慮なく質問ください。
まず、相談者の方から相談したいことを聴き取らせていただきます。その際に、ご準備いただいた資料も確認させていただきます。
その後、弁護士の方から、相談に対する回答をさせていただきます。
法律用語などの専門用語は分かりづらいことが多いので、図などを使いながら出来る限り分かりやすく説明します。
また、相談の対象にはなっていなくとも、対応しておいた方が良い問題が見つかった場合には、その点も併せて回答します。
その上で、事件をご依頼いただいた場合の処理方針や、タイムスケジュールなども説明します。
依頼した場合にかかる費用は、相談者から聞きづらい部分だと思いますので、弁護士から説明をさせていただきます(ご家族で相談をした上で決めたいというかたもいらっしゃいますので、見積も無料で発行いたします)。